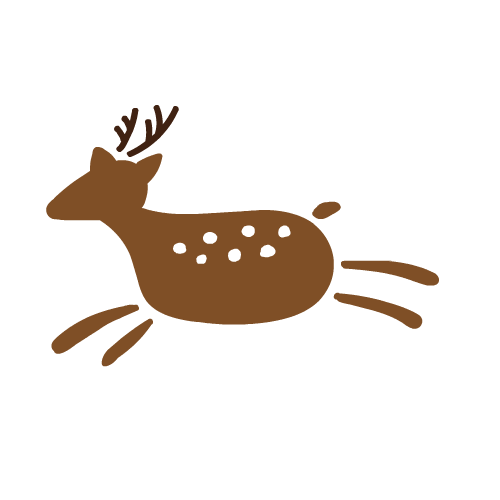春日大社国宝殿

主な収蔵品
神に捧げられた神宝 -王朝の優美な工芸品-
春日大社が所蔵する文化財の大きな特徴は、古来御神殿に納められ現代にいたるまで大切に守られ続けてきた宝物で構成されているところにあります。そのうち御本殿に安置されていたものを本宮御料古神宝類として292点、若宮御料古神宝類として49点が国宝に指定され、また古神宝銅鏡類17点や、単独で手箱も重要文化財に指定されています。これらは王朝時代に当時の技術の粋をもって制作された一級品ばかりです。
国宝 本宮御料古神宝類 蒔絵箏

弦の張られる龍甲部分には金・銀・銅粉の蒔絵粉を用いて墨流し風の文様をめぐらせ、樹々や草花、
国宝 本宮御料古神宝類 黒漆平文根古 志形 鏡台

根古志形鏡台は、脚の部分が木を根ごと
国宝 若宮御料古神宝類 平胡籙

重要文化財 秋草 蒔絵 手箱

長方形
武将の崇敬の証 -刀と鎧他武器武具-
春日大社には平安時代以降の各時代を代表する太刀が揃って残っています。飾剣(かざたち)、毛抜形太刀(けぬきがたたち)、兵庫鎖太刀(ひょうごぐさりたち)、革包太刀(かわづつみたち)などの各種の最高級品を所蔵しているのは春日大社のみで、その内8件25点が国宝に、8点が重要文化財に、7点が重要美術品に指定されています。さらに刀身が研ぎ減りの見られない生(うぶ)な状態なものが多く貴重です。
また春日大社では究極の豪華さと美しさを誇る国宝の赤糸威大鎧2領、機能美と優美さを兼ね備えた国宝の黒韋威の胴丸が2領伝えられています。これらは日本の甲冑の代表として様々なメディアで紹介されています。
国宝 金地螺鈿毛抜形太刀

本作は柄と刀身を
国宝 金装花押散兵庫鎖太刀

柄と鞘の全面を銀鑢地鍍金の板で包み、足金物などの金具は金鍍金で、目貫や責金具には桐紋が据えられている。帯執の兵庫鎖が固定化した蕪形となる南北朝時代の様式である。鞘・柄・鐔の全面に計24個の花押を墨書しているところが特徴的で珍しい。花押の形から足利一門のものと推定されており、社伝では足利義光奉納される。刀身は総長122.5㎝にもなり、身幅も広く大鋒で豪壮な大太刀である。刀匠銘はないが佩裏に「貞治四年卯月日」と年紀銘があり、備前国の長船兼光の作と考えられている。
国宝 赤糸 威 大鎧 (梅鶯飾) 兜・大袖付

大鎧は馬上での弓箭の戦いのために作られた甲冑で、室町時代以降は正式の甲冑ということから「式正の鎧」といわれる格式高い甲冑である。甲冑の名称は
国宝 赤糸 威 大鎧 (竹虎雀飾) 兜・大袖付

竹と虎と雀を基調として藤・桐・菊・蝶などを加えた飾金物を随所に配置し、頭上に大きく広がる金銅大鍬形は圧巻である。茜で染めた
国宝 黒韋 威 矢 筈札 胴丸 兜・大袖付

鹿革を藍で濃く染めた
国宝 黒韋 威 胴丸 兜・大袖付

黒漆盛上札を用いた黒韋威で、胴と
春日美術の世界 -春日曼荼羅と絵巻物-
美しい自然の中に春日社を描く宮曼荼羅や鹿の背に乗って神様が春においでになったという、 春日社創立の来歴を描いた種々の″鹿曼荼羅″その他、神様の使いである鹿を造形する様々な宝物が 伝わっています。 また春日明神の霊験の数々を描く雅やかな鎌倉絵巻の名品、春日権現験記。国宝殿には、 文化4年(1807)松平定信の自筆の奥書のある優れた模写本が収蔵されます。
奈良県指定文化財 鹿島立神影図 鎌倉~南北朝時代

春日本 春日権現験記

春日権現験記は春日明神の霊験の数々を示す説話を集めた絵巻である。平安から鎌倉時代の春日大社や興福寺の様子や、春日明神を氏神とする藤原氏の貴族から春日を信仰する庶民までの風俗が精緻に描かれており、読み解くほどに面白い。藤原氏一門である
芸能の美術 -舞楽の装束、面、楽器を中心に-
春日大社には、祭礼に舞われる芸能が伝承されると共に、その面や装束、楽器が伝承しています。中心は舞楽に関するもので、舞楽面は、重要文化財12点を含む、平安時代・近代に至る19種80点が、舞楽装束は桃山・江戸時代の約500点が伝えられています。また国宝の鼉太鼓をはじめ鎌倉・江戸時代の雅楽器約60点が伝来します。舞楽は5・6世紀に大陸より渡来した各種の楽舞が平安時代に整備され、国風化して定着した伝統芸能で、宮廷や社寺の儀式祭典に演奏されました。
重要文化財 舞楽面 納曽利

納曽利は高麗楽由来の舞で、二匹の龍が舞い遊ぶ様子を表現している。通常二人舞だが、一人で舞うときは落蹲という。但し、南都では二人を落蹲、一人を納曽利という。本作は目が動くような作り(動眼)で、下顎は面の内側の両目部分に通した棒に紐を吊るす釣顎であり、顎が動くと目も動く仕組みになっている。春日大社には本作を含めて重要文化財指定の納曽利の面が2面あり、そのほか室町時代作が2面と、江戸時代作が2面で計6面ある。室町時代と江戸時代作の4面は釣顎であるが動眼にせず眼球部分を彫り込んで固定化している。
重要文化財 舞楽面 散手

散手はひとりで舞う武の舞で、散手破陣楽とも呼ばれ、神功皇后が新羅軍を破ったのを率川明神が喜んで舞ったものと伝えられている。本作の裏に「以元興寺本模之/仏師定慶/寿永三年二月日」と刻銘があり、仏師定慶が寿永3年(1184) 元興寺に残る古面を模して制作したものであることがわかる。
舞楽装束 蘭 陵王 (袍 ・裲襠 ・袴 )

陵王は唐楽の走舞で蘭陵王とも呼び高麗楽・納曽利と